eGPUが完成して生成AIで遊ぼうという段階で色々調べたので、世の中どう変わるのかについて素人なりに概念的な方向性を少し考えてみた。
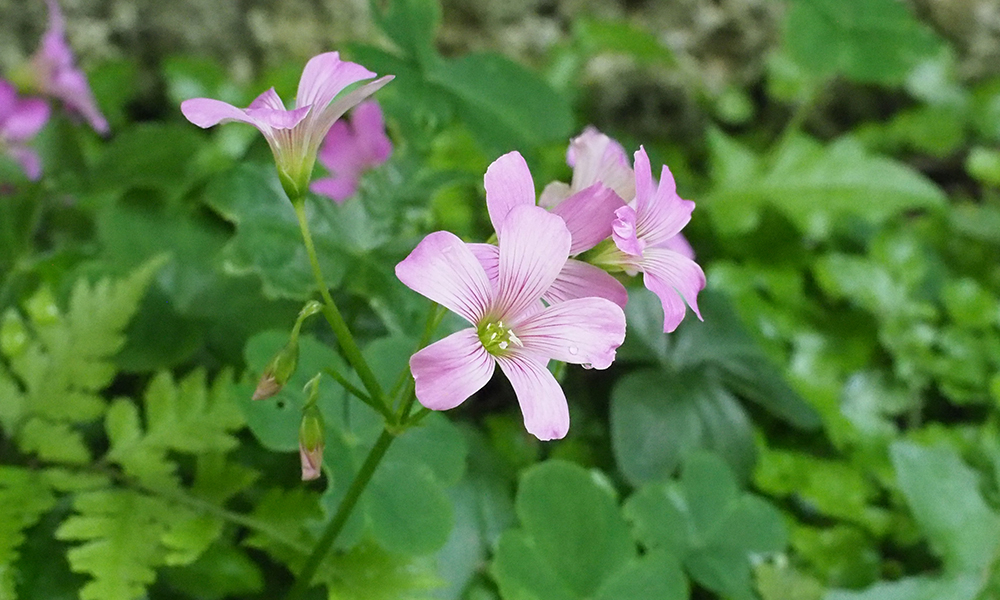
(今週の一枚)そろそろ春もおしまい(花盛り🌸)
世相から生成AIを見る
様々なAI技術使用を考えると、我々が人工知能(AI: Artficial Intelligence)と呼んでいるプログラムは大量な情報処理には良いがまだまだ欠陥がある技術だ。生成AIに関して、LLM(Large Language Model, 大規模言語モデル)や画像生成なんて要は情報を場合分けして平均化して、バイアスを何段階かかけて出力しているだけなので、入力情報量が多くても一定割合で必ず誤情報を出す。
この不完全な技術について、生成AIをリードする側ではシンギュラリティ(技術的特異点・AIが人間の知能を超える)により革命的な変化が起こるのではないかなんて言う人までいる。しかし、今の入出力方法では、理論上、情報処理の効率があがってもどうやってもシンギュラリティは起こらない。これに触れない点でかなり胡散臭い議論になる。シンギュラリティを起こすためにはシンギュラリティが必要で、そのシンギュラリティはきっとAIがシンギュラリティするから大丈夫だそうだ。馬鹿じゃないの?と思ってしまう。
そういった煽りに伴って、Xを中心に反AI運動みたいなものが活発に行われているが、そのほとんどが妄想や印象論だ。この反対論の多くが著作権の侵害問題と仕事がなくなるなどのぼんやりとした恐怖に支配されている。また、これらを煽って金儲けをする連中や単純に遊びや暇つぶしで喚き散らしている人が非常に多い。
それらを観察するに、良し悪しどちらの立場も極端に振れていると思う。
現実から見た世界の変化
では、これから世の中で何が起こるのか、生成AI利用を先行しているIT業界をモデルケースにすると予想がつくのではないかと思う。
現状、日本のIT業界は80万人を超える人材不足だと言われている。しかし、実際に経営側の話を聞くと、必要な人材が不足しているが人自体は余っているという。求められるスキルが大きく変わってきているそうだ。
ここ数年で簡単なコーディングやバグ取りは徐々に生成AIに仕事が移りつつある。早いし大体合っているし、徐々に精度が上がっているから、それは当然な流れなのだろう。一方で、新しいアイデアやどうやって利益化するかとか、UIなどのインターフェイス設計なんかは生成AIが不得意なよう(修正や仕様変更がやりにくい)で、むしろ生成AIをリードに使うと売り上げ減になる可能性もあるそうだ。
また、DX化に伴って仕事量は増えるが、IT土方なんて言われていたSEたちの仕事はここ数年で激減・激変する傾向だ。コードを書くのではなく、生成されたコードを管理・修正する作業への変化だ。必要となってくる仕事は、より感覚的なデザイン、依頼側とのコミュニケーション、生成AIを含むツールをどうやって使うかと言った一定の知識・経験を元に判断を下すものである。これらの人員が圧倒的に不足しており、仕事の質が徐々に変わっていることが現場の実感として在るようだ。
この先行事例から、我々の世界における生成AIの広がりは機械化・IT化されて、その修正や管理の工数が増加し、一方で、情報ストックにない人間の独創性が必要とされる仕事がどんどん増えると予想される。これが意味することは、総体の仕事量は減るどころか激増し、AI賛成反対両派閥が前提とすることと全く逆の現象(仕事の増加・管理の重要性)が起こる可能性が高い。
例えば、これを絵描きに当てはめてみる。同じようなハンコ顔や〇〇の描き方をそのまま描いている人、よく見るような背景を書く作業は駆逐されるが、生成AIで作ったものを加筆修正する作業が膨大化し、生成AIの外れ値として弾かれるような自分なりの描き方で作品を作る人や自分なりの世界観を持つ人はむしろもてはやされる可能性が高いのではないかと思う。
ネットによる分断の変化
上で書いた想定は、所謂、デジタル・デバイドが一層広がるのではないかということも示している。これはインターネットが普及した時やスマホが広がった時にも同じような現象が起こっている。では、どういった谷や格差が生まれるのだろうか?
例えば、ネットで知識を得るという点に焦点を当て、大雑把に解釈を書いてみる。
ネットが未発達の社会では技術や情報は特定個人や会社、政府と言ったある一定の場所に偏在し、使えるものと使えないものの格差が大きかった。プロとアマの大きな差みたいなものがあり、明確な谷となって存在していた。
情報のデジタル化に伴って、その谷はだいぶ埋め立てられたが、新しい格差は生まれた。例えば、ネットで誰かと会話をすると、ググレカスという造語・ネットスラングを投げられる時がある。これは「反射的に誰かに頼らず、まず、Googleなどを使って情報を調べ、それなりの知識を得てから自分の発現をしろカス野郎」という言葉だ。20年くらい前ならその通りだろう。この言葉が示すように、情報はあるが、1、検索しない人、2、検索する人の新しい2層に分かれていった。
しかし、10年くらい前のGoogleだとググったところで正しい情報が出ないことが多くなった。これはグーグルが検索サービスで支配的となり、利益化するために検索アルゴリズムを変えたからだ。自社の広告システムを使うサイトやより新しいページを優先的に表示するようになった結果、扇動的なサイトや不正確な速報性のあるページが検索上位に出るようになった。そのため、単純に単語を検索バーに入れただけでは正確な情報が取れなくなり、有効な検索方法を知らないと偽情報の取得や詐欺にあう可能性がとても高くなった。つまり、ツールの変化と情報量の増加により、1、検索しない人、2、チョット検索していい加減な情報を得る人、3、ちゃんと検索して正しい情報を得る人という大雑把に3層の分断になった。
さて、ここ数年は生成AIの登場だ。グーグル検索には「AIによる概要」と「関連する質問」というものが検索後のトップに出るようになった。これはLLMによる回答を載せたもので、より確からしいサイトの情報を200字くらいでまとめたものだ。これを読むと色々ごちゃごちゃ調べたりせず、最低限必要な情報が得られるようになってとても便利だ。しかし、この概要は誤りが多く、パッと見てパッと判断できるが、それを前提知識にすると大きな失敗をする。結局、必要な情報を得るためにはさらに手間をかけて調べないといけないことになる。つまり、便利な生成AI導入によって、一見、検索する人としない人の2層に戻ったように見えるが、3層分断は維持されたままなのだ。
ここからわかることは、元情報量が増加しない場合、生成AIを利用することで新しいことは何も起きず、総体の効率化も起きず、層間の人員の入れ替えが起こっただけだとわかる。大雑把な解釈だが、デジタル・デバイドは「正確な情報へのアクセスのしやすさ」とその習得情報量の増減が重要のようだ。
情報の価値
では、正しい情報や新しい情報とは何なんだろうか?
正しい情報に関しては近い分野でもその幅は大きく異なる。例えば、数の学問だ。算数なら答えは一つだろう。高校数学なら複数解かもしれない。大学以上の数学なら、その概念自体が数年おきに変わることがあり無数の答えがでる可能性もある。
つまり、単純な低いレイヤーでは単純で正確な情報はあるが、複雑な高いレイヤーでは正確な情報はそもそも存在しないか、場合によっては新しく作り出さないといけないことになる。
生成AIが担える情報はおそらく基礎情報が固定された単純で低いレイヤーであり効率的に処理できるが、複数の答えを持つものや評価値が変動する新しいものの定義は今のところ難しい。
また、人間が求める「新しい情報」も定義が難しい。若者が何十年前のファッションを新しいと感じても、社会としては情報がただ繰り返されただけである。老人が昔見たファッションを新しいと見なすには何かワンポイントでも違いが必要だ。
例えば、上のミュージックビデオは10年近く前のものだが現在でも初めて見る人にとっては新奇性を感じるだろう。この人はどうなってしまうのか、ついつい見てしまう。女性の創作ダンス、VFXによる合成、テクノ調のミュージックと繰り返しの歌詞、これらは単体ではどこかで見たような情報だ(VFXは当時最新?)。しかし、これをうまく組み合わせて一つのものにすると新しい情報に見える。
そのため、新しい情報とはその繰り返しの中で新しい概念や技術を少しずつ混ぜることで成立するものかもしれない。
おそらく、この記事の一番上でリンクを張ったAI2027ではこういったものを生成AIが作ることでシンギュラリティが起こると言いたいのだろうが、自分には厳しいと思う。どれだけランダム性を持たせても、結局、出力したものを判断するのは人間であり、元情報が同じなら新しいプログラム主体(人間でいう新生児)は現れず、パーセプトロン(入力→計算→出力)を前提としたシステムは既存の概念のままだからだ。
仮に人間の別の神経回路システム(カルシウムウェーブによるゆっくりとした情報伝達、過去の記憶を現在得た情報に修飾しての処理、電気生理学的スパイクのリズム化など)を模倣した技術ができたとしても、トレードオフで処理自体を遅くすることになり、人間や動物を超えるのは難しいのではないだろうか?
また、情報の価値はある環境でそこに生きる人間が決めるものなので、環境や人間が変化する限り、価値そのものが変数となり答えが出ない。情報に価値を持たせる点では、固定した解を出す現状の生成AIは無力だと思う。
結論
世の中はわいわい騒いでいるから、面白いものはたくさんできるだろう。色々な事柄が効率化するだろう。でも、その効率化の先には別の面倒があり、その面倒で苦労することになり、日々の仕事は増えることはあっても減ることはないだろう。
個人は乗り遅れないようにうまくこの新しい道具を使いこなすことが重要だ。
終わりに
なんか面白いことができればいいなぁなんて思っているけど、なかなかそれを思いつかない。新しい発想がでないということは、もしかしたら自分は旧世界ポンコツAIの成れの果てなのかもしれないな(^ω^)
☆エロ同人CG販売中




